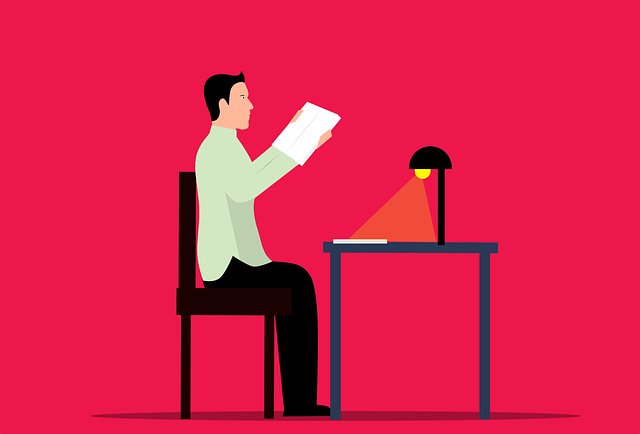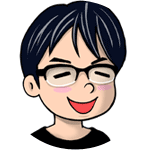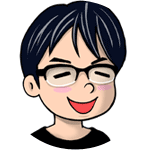 サト
サトこのたび、「日本語教師のための『多読』」というセミナーに参加してきました。
講師は、NPO多言語多読の粟野先生!
「多読」について詳しいことはNPO多言語多読公式サイトを見ていただくのが一番なので、この記事ではわたしが感じたことを中心にシェアしたいと思います。
多読のルールは、ちゃんと多読をするためにある
「多読」というのは、文字通りたくさん読むことなのですが、今回のセミナーでは「楽しくたくさん読むこと」と教わりました。
その多読には、多読3原則というものがあります。それは、次のとおり。
多読3原則
- 辞書は引かない
- 分からないところは飛ばす
- 合わないと思ったら投げる
NPO多言語多読公式サイトより引用しました。
セミナーでは、上の3つに「やさしいものから読む」を加え、「4つのルール」という名前になっていました。
と言っても、サイトにも「『多読3原則』を使ってごくやさしい絵本からはじめ、〜」と書いてあるので、(当然ですが)同じことを言っています。
とにかく、このルールは、「楽しくたくさん読む」ためにあるんやなあ、と思います。
- 辞書は引かない→時間の節約につながる
- 分からないところは飛ばす→時間の節約につながる+悩まない
- 合わないと思ったら投げる→自分に合う本を選ぶ
- やさしいものから読む→たくさん読める
逆に言えば、辞書を引くのに時間がかからなければ引いてもいいのかなあ、という疑問も出てきてしまいました。
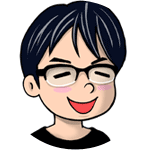 サト
サトセミナーの際に「NPO多言語多読」の問い合わせ先のメールアドレスを教えていただいたので、ちょっと聞いてみました。
すると、なんと同NPOの理事である繁村先生から直々にお返事が!
結論から言うと、時間がかからない場合でも、辞書を引くことは推奨していないとのことでした。
数秒であっても、英語の世界から現実に引き戻されてしまうためです。
それなら、英英辞典はどうかと思い、再度問い合わせたところ……。
次の条件を満たすなら、まだ許容範囲である旨のご回答をいただきました。
- 辞書に頼るクセから抜け出した段階にある
- 本を読み終えた後に辞書を引く
いちいち辞書を引かないと読み進められない段階を脱し、かつ、1冊読み終えたあとなら、という条件ですね。
ただし、この場合も辞書の使用を積極的にすすめているわけではありません。
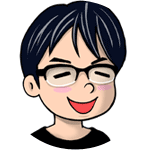 サト
サト多読の注意点(経験者談)
今回参加したセミナーでは、グループワークの時間もあり、多読をすでに実践されている先生のお話を聞くことができました。
そして、多読を実践するにあたって、注意すべき点も教えていただきました。
- 学生が読める本がなくなってしまう(弾切れ)ケースもあり
- 本が増えると管理や運搬が大変
- PDFもいいが、学生の達成感は紙の本のほうが上
③のPDFよりも紙の本のほうが達成感があるという話ですが、この点は工夫すればそこそこカバーできるような気がしています。
わたし自身、最近英語の多読を始めたのですが、電子版でも洋書を1冊読み切ったときはかなり達成感を感じたからです。
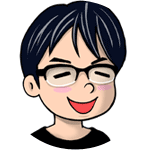 サト
サト何せ、紙の本のページ数は、232ページ!
たしかに紙の本で厚みを感じながら読んだほうが達成感はありそうですが、紙の本が無いなら無いなりに、達成感を味わう方法はありそうです。
まずは紙の本を利用して達成感を得てもらい、ページ数も記録。
電子版を利用する場合もページ数を記録してもらうことで「だいたいあの本と同じぐらい読めたか」と感覚で達成感が得られるかもしれません。
能力試験対策としても効果あり!
今回、わたしがセミナーに参加して一番聞きたかったのは、多読が日本語能力試験にも効果があるのかどうか、という点でした。
結論から言うと、あるとのことです!
たとえば、日本在住の中学生(1年生)が、日本語の「勉強」は多読+模擬試験数回だけで、日本語能力試験1級*に合格したんだそうです!
*旧試験か現行の試験かは聞きませんでした
日本に住んでいても、1級やN1にはそう簡単に合格できるものではありません。
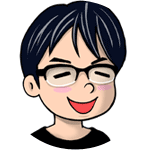 サト
サトわたしの職場の学生も、日本留学経験者は何人かいますが、今のところN2が最高ですし。
このお話は、楽しく能力試験対策をしたいと思っていたわたしは朗報でした。
問題集が中心だと、やっぱり飽きてくるんですよね……。
学生も、わたしも。
セミナーが終わってからまだそんなにたっていないのですが、学生にはひとまず多読の方法や効果などを伝え、希望者に多読用の本の貸出を行っています。
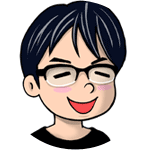 サト
サトすぐに結果が出るものでもありませんが、これからが楽しみです!
ちなみに、英語の多読がTOEICに効果があるというのは、次の本を読んで知りました。
わたしのメールに丁寧に応えてくださった、繁村先生の本です!
その他(質疑応答より)
その他、こんな質疑応答がありました。
学生が読みたい本が難しすぎる場合はどうするか
基本放置し、読みたい本は読ませつつも、たまに「こんな本もあるよ」と提案。
多読を始めるに当たり、なにかアドバイスはあるか
ささやかに始めること。
ただし、教室で多読をする場合、最低30分はほしい。
時間が短すぎると本にのめりこめないため。
まとめ
この記事では、「日本語教師のための『多読』」というセミナーに参加して感じたことなどをシェアしました。
ご参考になれば幸いです!

なお、第二言語習得を英語学習にどう活かすかを解説した記事もありますので、よろしければどうぞ。